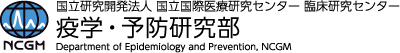第136回検討会概要《日本におけるワクチンを含む予防や治療の今後の戦略/職域での感染症予防対策の事例》
前の記事 | 次の記事開催概要
日 時:2025年3月8日(土)14:00-17:00
場 所:TKP神田ビジネスセンター
特別講演:日本におけるワクチンを含む予防や治療の今後の戦略
講 師:大曲 貴夫 先生(国立国際医療研究センター)
抄 録:日本の感染症危機管理において、COVID-19対応の経験から、特に以下の3点が不足していることが明らかになりました。1つ目は、平時からの備えの不十分さです。迅速な情報発信や医療提供体制の強化、専門人材の育成、研究開発への投資が求められていましたが、これらの準備が不十分であったため、感染拡大への対応が遅れました。2つ目は、変化する状況に適切に対応する柔軟性の欠如です。感染状況の変化に応じた対策の切り替えが難しく、迅速な判断が必要な場面で適切に対応できないことが課題として挙げられています。3つ目は、正確な情報発信と共有の不足です。誤情報や偏見が蔓延し、国民に対するリスクコミュニケーションの強化が求められました。
これらの課題に対応するため、政府は新型インフルエンザ等対策政府行動計画を改定し、感染症対応機関の新設、ガバナンス強化、そしてデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進を通じて、次の感染症危機に備えるための体制整備を進めています。また、国立健康危機管理研究機構の設立により、国際連携や包括的な感染症研究・人材育成が図られ、今後の危機管理能力がさらに強化されることが期待されています。
また、パンデミックでは個人を守り社会活動を早期に正常化させる上での診断薬、治療薬、ワクチンなどの感染症危機対応医薬品等の重要性が明らかとなりました。特にワクチンについては、研究開発だけでなく緊急時の集団的な接種体制の構築と運用が極めて重要であることもわかりました。平時からの準備も欠かせません。当日はこの点にも触れたいと思います。
教育講演:職域での感染症予防対策の事例
講 師:堀 愛 先生(筑波大学)
抄 録:本講演では、職域のワクチンで防げる感染症対策の実例として、季節性インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風疹、およびHPVワクチンを取り上げて考察します。
職域の感染症対策における産業医の役割は、事業者が感染症対策と事業継続との両立を図るための助言指導を行うことです。事業者は不確実性の中での意思決定を迫られることになりますので、産業医は、最新の医学情報の収集に努めて、感染症のリスクアセスメントを実施し、公衆衛生上の態度を示すことが求められます。このとき、リスクの重篤性の判断が評価者によって異なることを前提として、多様な視点を持つことが必要です。産業医が事業者に助言指導するにあたって、関連法令(感染症法、労働基準法、労働安全衛生法、学校保健安全法)や、感染症対策の社会的意義(安全配慮義務、企業の社会的責任CSR、健康経営、SDGs)の理解が重要であることは言うまでもありません。感染症の多くは、他の職業病と同様に予防可能です。特に、一次予防である予防接種の普及推進に産業医が果たす役割は大きいと考えます。
総合討論:職域における感染症対策
ファシリテーター:堀 愛 先生(筑波大学)
抄 録:COVID-19学会ガイド等を有志で作成したが、次のパンデミックでは同様の成果物を出せない懸念があり、国の危機管理体制に産業保健部門を設置する必要性が指摘された。事前アンケートで、COVID-19臨時接種を8/13名が実施していたが、企業独自の交差接種は認められなかった。COVID-19対策緩和に際しては、医学・経済学など専門分野による主張が食い違う場面があったが、高齢者・女性・子供などの属性による命の価値について、公に議論されないままであった。また、良好な双方向のリスクコミュニケーションの事例として、積極的なアウトリーチや、当事者の話を聞くことの重要性が議論された。